株式分散の経営上のリスクや対応策を解説

会社経営者や創業者一族は会社経営だけでなく、事業承継時に「株式」について考えなければならないことが数多あります。
株式が分散している場合に事業承継に悪影響を及ぼす可能性があるため、経営者の頭を悩ませる大きな問題になります。
そこで今回は株式分散とはどのようなものか、また、株式分散で起こりうるトラブルの内容について触れると共に、株式分散への対応策についてわかりやすく解説していきます。
株式分散とは

株式分散とはどのようなものかについて説明していきます。
株式分散とは会社が発行する株式が一人によって保有されている状況ではなく、少数の株主が多数いるような状況で「複数人が株を保有している状態」を指します。
文字通り分散して株式が複数人に保有されている状況です。
通常、上場企業などの会社運営の中で分散株式が発生することは珍しいことではありません。むしろ、当たり前と言って良いでしょう。
特に業歴が長く古い会社になればなるほど株式分散が発生しやすくなり、実務上、多くの方が株式を保有しているというケースも多いでしょう。
事業運営の中では特にこの株式分散が問題になる事はありません。
しかし、この後ご紹介するようなタイミングでは株式分散によって様々なトラブルが起こる可能性があり、特に非上場企業は注意すべきです。
株式分散が起こる原因

株式分散が発生する原因について、いくつか「よくあるもの」をまとめてご紹介していきます。
名義株の存在
まずは名義株の存在が一つ原因として考えられます。
そもそも名義株とは、株主名簿に記載されている株主の名前と実質的に株式を所有している人が異なる、つまり「実質的な株主と名義上の株主が異なる株」のことを言います。
名義株が発生する理由については様々ありますが、相続税を回避するため子供を株主の名義にしていたが、実質的株主は親だったというケースも見られます。
このような株主は株式の持分を持っていますが、所有権を正式に証明する証券がないため、株主名簿に記載されないといった特徴があります。
創業時に不特定多数から資金援助を受けていた
例えば業歴の長い会社などでよくあるケースとして、創業時に創業者が地元の方々やご友人など、不特定多数から資金援助を受けていたというケースが考えられます。
この場合も少数の株主が複数存在することになるので、分散株式が存在することになるでしょう。
また先ほど述べた通り、こういったケースでは分散株式がさらに投資出資あるいは資金提供を行った方がすでにお亡くなりになっており、1世代あるいは2世代にわたって相続され、現在の株主が不明というケースになることもあるでしょう。
上場計画が中断された
不特定多数から出資を受けるケースとして、上場計画があり、会社の株主を増やしていたというケースも考えられます。
こういったケースでは計画が立ち消えになるなど、往々にして払い戻しなどの事後処理が行われていないケースもあり、会社の経営陣との考え方が異なるような少数株主が多数存在することもあります。
株式分散で起こりうるトラブルやリスク
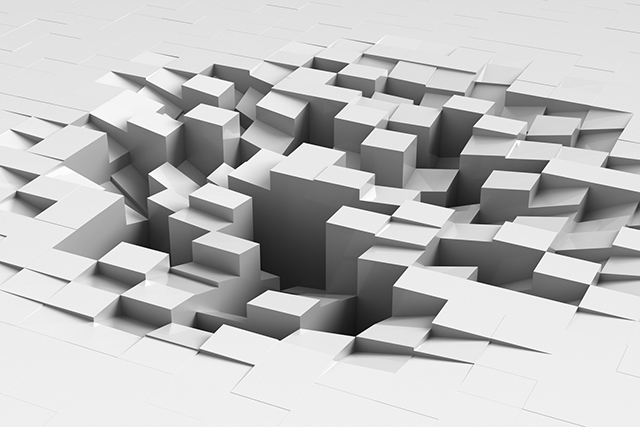
それでは株式分散があることによって起こりうるトラブルやリスクについて、ご紹介していきます。
「真の株主」が見つからなくなる
先ほども紹介した通り、株式分散の中には名義株と呼ばれるものも多々存在するため、状況によっては名前や住所がわからない実質的株主も存在することがあります。
つまり、「真の株主」の所在が分からず、適切な議決を取れない恐れがあります。
このようなケースでは会社にとって重要な決議を行う際に株主からの同意を取り付けることが難しく、特別決議を議決できなくなるといったリスクが想定されます。
特別決議の際に悪影響を及ぼすリスクがある
上記で述べた通り、特別決議の際には議決権を持つ一定数以上の株主による同意が必要なケースがほとんどです。
よって分散株式を放置してしまうと、株主が分散されているため特別決議など重要な決定を行うにおいて数段階ハードルが上がってしまうケースがあります。
その他、株主の分散は会社の運営に悪影響をもたらす可能性もあるでしょう。
具体的には会社の存続を左右するような大きな決議がある際に株主の意見を一本化することができず、また予想だにしないような角度から少数株主が結託して創業家に悪影響のあるような動議を行う可能性もあります。
株式分散の対応策について

ここでは株式分散が発覚した場合に会社としてどのような対応を取るべきなのか、またオーナーとしてどのような対応を取るべきかについて、わかりやすく解説していきます。
資金負担によって株式分散を集約する
まずは資金を投入して株式分散を集約することができます。
具体的には、少数株主から株式を買い取り、安定株主を増やすことで株式の分散状態を解消する方法です。
ただし、これには多くの費用が必要となること、また、株主の所在が分かっており、株主の同意などが必要となります。
株主の同意が得られず、株式分散を集約できるとは限りません。難儀する恐れも十分に考えられます。
特に三代目社長などになると、創業者と関係が深かった当時の株主とは関係性が希薄になっているケースも考えられ、交渉が難しいという覚悟も必要です。
分散株主との関係性を強化していく
株式分散を集約せず、少数株主が複数存在することを認識したまま少数株主との関係性構築・強化を行なっていく方法もあります。
それが分散株主との関係性を強化する方法です。
敵対する株主よりは、味方になってくれるような安定株主になってもらえるように関係性を強化します。
これにより決議事項が生じた場合も、経営陣の望む方向で決議をしてもらうことが可能となるでしょう。
ただし、確実に株式分散を集約しているわけではありませんので、土壇場になって翻意される可能性もあります。
コミュニケーションの部分では特に丹念な取り組みが必要となります。
なにより、この経営陣なら経営を任せても大丈夫だと思ってもらえるような経営手腕が求められます。
制度を活用して株式を集約する
一定の要件を満たすと分散株式を集約できるような制度や仕組みがあります。
そのような制度を使って株式を集約する方法もあります。
例えば、以下のような制度があります。
- 所在不明株主の株式売却制度
- 特別支配株主による株式等売渡請求
これらは株主総会の決議は必要なく、集約することが可能です。
また、株主総会の特別決議は必要ですが、少数株主の株が1株未満となるような株式の併合を行うことで株を集約する方法もあります。
いずれにしましても手続きが煩雑ですので、どの方法がベストな集約方法か検討を重ねる必要があります。
まとめ

今回は株式分散に関して、あらましや起こる原因のほか、対応するための対策について解説してきました。
株式分散は事業運営上、特段の悪影響を直ちにもたらすものではありません。
しかし会社にとって重要な決議を行う際は、分散株式がその障害となり得る可能性は十分に考えられます。
よって早い段階から株式分散があることを認識し、その対応策を取っていくことが重要となるでしょう。
また、株式分散の対応については法律に則るのはもちろんのこと、戦略的かつ効率的に行っていく必要もあります。
こうした事案では当社がお役に立てます。まずはお気軽にご相談ください。
