寄附で相続税が安くなる?寄附金控除のあらまし&注意点を解説します

「遺産を相続した時、寄附をすることで相続税が安くなる」といった話を耳にされたことのある方も多いかも知れません。
これは結論から言えば正しい情報です。寄附金控除というものがあり、これによって遺産を相続した際、その一部を寄附することによって相続税を安く抑えることができます。
今回はこの寄附金控除について詳しく説明していきます。
相続税が安くなる?相続税の寄附金控除とは
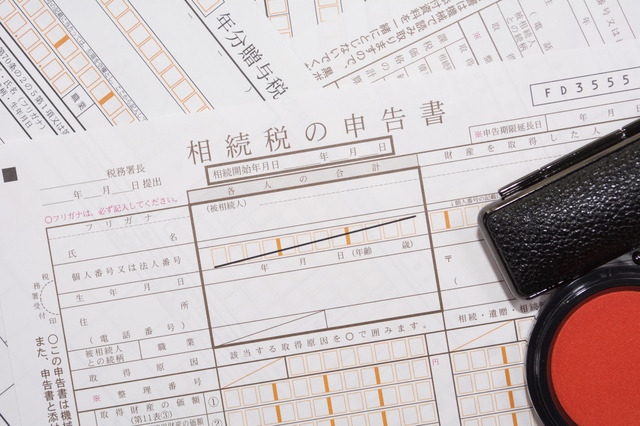
まず、そもそも相続税とは何かをおさらいしておきましょう。
相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産(や債務)を引き継ぐ人に対して課される税金のことを指します。
そして、この相続税には特例として、寄附金控除という制度が設けられています。
この制度は、簡単に言うと「相続した人が、自分の意思によって国・地方公共団体、あるいは公益財団法人等特定の団体に寄附をした場合には、その寄附額が相続税課税の計算対象から差し引かれる(非課税となる)」というものです。
なお、この寄附金控除については寄附行為を行うことによって相続税が非課税になると勘違いされる方がよくいらっしゃいます。
実際には寄附行為を行った金額が非課税の対象になるというだけで、現実的には相続税を納税しなければならないことになります。
ということで、大幅な節税効果があるというわけでは残念ながらありません。
また後述するようにいくつかのメリットはあるものの、どちらかというと注意点やデメリットも多い制度となります。
よって寄附金控除を行う場合にはメリットやデメリットをきちんと理解した上で活用する必要があります。
寄附金控除を受けるために必要な要件・条件等まとめ

ここでは寄附金控除を受けるために必要と定められている、いくつかの要件や条件についてまとめてご紹介していきます。
要件・条件1:国又は地方公共団体中古公益法人等であること
寄附金控除を受ける際に寄附をする先はどこでもよい、というわけではありません。
いわゆる国そのものであったり、地方公共団体、その他特定の公益法人等への寄附の場合のみ寄附金控除が認められるということを理解しておく必要があるでしょう。
具体的には認定NPO法人であったり、特定公益増進法人であるなど、いわゆる教育及び科学振興等に貢献する度合や著しい特定の公益性の高い法人が寄附先として認められています。
要件・条件2:相続した財産のままの形で寄附をすること
これは端的に、相続した財産以外の形で寄附金控除を受けることは認められていないということです。
つまり相続した財産をそのままの形で寄附しなければ、寄附金控除として認められないことになります。
よくあるケースとして不動産や有価証券などの現金ではない財産として相続したものを売却および換価し現金にしてから寄附をするというケースが見られます。
こちらについては寄附金控除として認められないのでご注意ください。
要件・条件3:申告期限内に寄附を完了していること
大原則として相続税は、被相続人が亡くなった日の翌日から起算して10ヶ月が納税期限と定められています。
よってこの10ヶ月という申告期限内に相続した財産の寄附を完了している必要があります。
亡くなった日の翌日から1年後に寄附をしても、寄附金控除は認められないばかりか、この場合相続税の納税期限を超過しているため様々な問題が生じることになります。
寄附金控除における注意点は?

それでは寄附金控除を行うにおいて、どのような注意点があるのかについて解説していきます。
注意点1:被相続人の遺言による寄附は対象外
亡くなった方、つまり被相続人の方が亡くなる前に遺言で特定の団体等へ寄附をするようにと言い残していた場合、こちらについては寄附金控除の対象外となります。
あくまでも被相続人が自らの生前の意思によって寄附を行うよう遺言している場合、相続人が寄附行為を行ったとしてもそれは相続人の意思によるものではないとみなされ、結果的に制度の対象外となってしまうわけです。
注意点2:寄附金受領証明書の添付が求められる
寄附金控除を受ける場合には、寄附金受領証明書を寄附した相手から発行してもらう必要があります。
一般的には財産の贈与を特定の団体等が寄附行為によって受けたという内容の他、寄附行為を受けた具体的な日付、寄附された財産の内訳や詳細等に関する情報が必要となります。
この寄附金受領証明書を添付のうえ相続税を申告することによって、寄附金控除が初めて適用されることになるため十分にご注意ください。
注意点3:寄附先と特定の利害関係がある場合に注意
寄附金控除が受けられる特定の寄附先については先ほど述べた通りですが、この時、寄附先等との間に特定の利害関係があり、寄附行為を行ったことによって寄附をした人物あるいはその家族等が寄附先の団体から特定の利益を受けるような場合は注意が必要です。
この場合、いわゆる相続税の課税逃れをしていると判断されることもあり、不利益な処分を被ることがあります。
まとめ

今回は寄附行為を行うことによって相続税が安くなる寄附金控除について、そのあらましや注意すべきポイントについてご紹介してきました。
この他にも相続税の節税を見込む場合は税の専門家へ相談されることをお勧めしております。
リガーレでは税理士が所属しておりますので、相続に関する様々なご相談のご対応が可能となっております。
