酒蔵業界のM&A動向について

日本の伝統産業の一つと言える酒蔵は、消費者行動の多様化や人材の高齢化により、変革の時を迎えています。
この記事では、酒蔵業界の課題や展望、M&A事例やメリット、M&Aを進める上での留意点などをご紹介します。
酒蔵業界とは
まずは、酒蔵業界の定義や特徴について解説します。
酒蔵業界の定義・特徴
酒蔵業界の定義について説明します。
酒蔵業界とは、米、米麹、水を主原料とする日本酒の生産、流通、販売、及び関連するサービスを提供する企業や団体、そしてこれらに関わる市場全体を指します。
日本国内の酒蔵の事業者数は約1,100者と言われており、都道府県別では新潟県、長野県、福島県に多く点在しています。
一方、売上高においては、酒蔵業界の大手企業が本社を構える地域が多くなる傾向にあります。

(出典:国税庁「酒類製造業及び酒類卸売業の概況(令和3年調査分)」から引用し、リガーレにて作成)
酒蔵業界の商流
酒蔵業界の商流を以下に示します。

(出典:日本酒造組合中央会「日本酒の製造工程」を引用し、リガーレにて作成)
1.酒蔵
酒蔵は日本全国に点在していますが、これらの酒蔵は地方ごとに異なる気候や水質、風土を生かして独自の日本酒を作っています。
大手酒造メーカーから、地元に密着した小規模な酒蔵までさまざまな規模の生産者が存在します。
2.卸売業
生産者から日本酒を買い取り、飲食店や小売店に供給、あるいは海外に輸出する等の流通機能を担っています。
3.小売業者
家庭用として一般消費者向けに日本酒を販売する業態としては、大規模な小売業者であるコンビニエンスストアやスーパーマーケット、さらには日本酒専門の酒屋やオンラインショップを展開する専門店があります。
また、業務用としては居酒屋、レストランなどの飲食店にて日本酒が重要なメニューアイテムとなっています。
酒蔵業界の現状
酒蔵業界の現状は、国内市場の変化や海外市場の拡大、新しい消費者層の獲得など、さまざまな要素が絡み合っています。以下に、酒蔵業界の現状について詳しく説明します。
1.国内の日本酒離れ
日本国内の日本酒消費量は、1980年代をピークに減少傾向にあります。
少子高齢化や若者のアルコール離れが主な原因です。
また、嗜好の多様化によって、ワインやクラフトビール、ハイボールなどの他のアルコール飲料が人気を集めていることも、日本酒の消費減少の一因になっています。
2.新しい消費者層の獲得
若者や女性向けにフルーティーな香りや軽い飲み口の日本酒、新しいパッケージデザインの商品が増えています。
このように差別化と同時に高付加価値化を進め、単価を上昇させ、新たな成長の機会を創出する事業者も少なくありません。
他にも、日本酒を気軽に楽しめるイベントや試飲会が開催され、新しい消費者層の獲得が進んでいます。
酒蔵見学ツアーやイベントを通じて、観光客に日本酒の魅力を伝え、直接販売を促進しています。
地域の特産品としての日本酒の認知度を高めるため、地方自治体との連携が進んでいます。

(出典:国税庁「酒のしおり(令和5年6月)」)
3.海外市場の拡大
日本食ブームに伴い、アメリカ、アジア、ヨーロッパなどの海外市場で日本酒の需要が増加しています。
海外の消費者が日本酒の品質や多様性を認識するようになり、輸出量が増加しています。
これに乗じて、各地の酒蔵や日本酒団体が海外でのプロモーション活動を積極的に行い、日本酒の認知度を高めています。
国際的な酒類コンテストでの受賞が増え、日本酒の品質が評価される機会が増えています。

(出典:国税庁「酒のしおり(令和5年6月)」)
酒蔵業界が抱える課題と展望
ここでは、酒蔵業界が抱える課題と展望について、述べていきます。
酒蔵業界が直面する主な課題
1.少子高齢化
少子高齢化により、国内市場の消費人口が減少しているため、新たな市場開拓が必要です。
高齢者向けの軽い飲み口の日本酒や、健康志向に対応した低アルコール日本酒の開発が進んでいます。
2.酒蔵の後継者不足
多くの酒蔵が後継者不足に直面しており、技術や伝統を維持することが難しくなっています。
地域の酒蔵同士の連携や、若者向けの研修プログラムを通じて、次世代の醸造家を育成する取り組みが行われています。
3.技術革新と品質管理
高品質な日本酒を安定して生産するために、最新の技術や設備の導入が進んでいます。
持続可能な生産方法や環境に配慮した製造プロセスの導入が求められています。
酒蔵業界の展望
酒蔵業界の展望は、国内市場の変化や海外市場の拡大、新技術の導入など、さまざまな要因によって形成されています。
以下に、酒蔵業界の今後の展望について詳しく説明します。
1.海外市場のさらなる拡大
日本酒の輸出は年々増加しており、特にアメリカやアジア、ヨーロッパでの需要が高まっています。
今後は、アフリカや南米などの新興市場への進出も進むと予想されます。
今後もこれらの市場におけるプロモーション活動や現地のパートナーとの連携が強化されると期待されています。
2.国内市場の再活性化
高品質で特別な製造方法を用いたプレミアム日本酒の需要が増加しており、これにより国内市場において高付加価値商品の展開を拡げることが期待されます。
また、地域特産の原材料を使用した限定商品や、地域の文化を反映した日本酒が増えることで、地域経済の活性化と連携が進むことも予想されています。
3.技術革新と生産効率の向上
最新の醸造技術や設備の導入により、品質の向上と安定した生産が可能になります。
さらに、IoTやビッグデータを活用した生産管理や品質管理が進み、生産効率の向上とコスト削減が期待されます。
また、持続可能な生産方法や環境に配慮した製造プロセスの導入が進むことで、環境負荷を減らしつつ高品質な日本酒を生産することにも繋がります。
環境に優しい日本酒として、エコラベルを付与するなど、消費者の関心を引き、ブランド価値を高めることが期待できます。
4.観光との連携強化
酒蔵見学ツアーや日本酒イベントを通じて、国内外の観光客を呼び込み、直接販売やブランド認知度の向上を図れます。
地域の観光資源と連携し、地域全体の魅力を高めることで、観光と日本酒産業の双方が活性化することが期待されます。
また、酒造り体験や試飲会など、体験型プログラムの充実が観光客の関心を引き、リピーターの獲得につながります。
5.人材育成と継承
多くの酒蔵が後継者不足に直面しています。
後継となる経営者もさることながら、酒造りの職人である杜氏の技術は、まだまだ人に帰属している部分が多く、次世代の醸造家を育成することが重要です。
若手醸造家の育成を目的とした研修プログラムや、専門学校、大学での教育が進んでいます。
酒蔵業界のM&A事例と活用のメリット
日本の伝統産業の一つである酒蔵業界ですが、国内マーケットの縮小や後継者問題などの課題を抱えています。
これらを解決するために、M&Aは有効な手段の一つと言えます。
ここでは、酒蔵業界のM&A事例や、売手・買手双方のメリットについて、詳しく説明します。
酒蔵業界のM&A事例
伝統蔵が盛田を買収
2022年、株式会社伝統蔵は、株式会社JFLAホールディングスの子会社である盛田株式会社が保有する各酒造会社10社を、株式譲渡により取得。
伝統蔵は、酒類関連のコンサルティング業務を行っている。
株式会社JFLAホールディングスは、本譲渡を組織再編による収益力の改善を目的としている。
コロナ禍や円安の進行により、本業である販売・流通事業の業績が低迷。
加えて、大豆・小麦等の穀物価格や重油等のエネルギー価格が高騰し、主力事業である生産事業においても収益率が悪化していた。
そのような状況の中、伝統蔵よりMBOの方法にて各酒造会社の酒類製造・販売事業について譲受要請があり、検討の結果、経営改善計画にも資するものと判断し本件に至った。
夢酒蔵が吉田酒造を買収
2022年、月桂冠OBが設立した夢酒蔵株式会社が、滋賀県高島市の吉田酒造有限会社の全株式を取得。
夢酒蔵株式会社は、後継者不足や経営に窮した中小酒蔵を譲受け、経営の改善や成長を目指す企業。
一方、吉田酒造は、1877年創業の老舗酒蔵で、「竹生嶋」ブランドを展開する。
本件により、吉田酒造の後継者問題の解決の他、新銘柄の創出、海外への販路拡大を企図している。
株式会社Clearが有限会社川勇商店を買収
2018年、日本酒専門メディアである「SAKETIMES」を展開する株式会社Clearが、有限会社川勇商店の全株式を取得。
これにより、酒類小売業免許を取得することができ、新たに酒類販売事業を展開し、事業の多角化を実現している。
売り手側のメリット
1.後継者問題の解消
酒蔵業界の中小企業では後継者問題が深刻化しているケースが多いです。
M&Aを通じて経営権を買手企業に引き継ぐことで、オーナーの引退後も企業が存続し、従業員の雇用も守られることになります。
2.経営の安定と持続性の確保
国内の日本酒需要低迷などのマーケット環境において、中小企業は規模の小ささゆえに経営リスクが大きく、経済状況の変動や市場競争の激化に対して脆弱です。
M&Aを通じて大手企業や資金力のある投資家に買収されることで、経営基盤が安定し、持続的な成長が期待できます。
3.海外市場へのアクセス
日本酒の人気は海外でも高まっています。
M&Aによって、海外市場に強い企業やネットワークを持つ買収先と連携することで、売手企業は新たな市場に迅速にアクセスすることが可能になります。
これにより、グローバルなブランド認知度が向上し、売上の増加が期待できます。
4.原材料の安定供給
日本酒の品質は原材料である米の品質に大きく依存します。
M&Aを通じて、原材料供給の安定を図ることができるため、品質の安定化とコストの最適化が実現します。
5.事業の最適化と効率化
M&Aにより、重複する業務や非効率なプロセスの見直しが行われ、経営の効率化が図られます。
また、シナジー効果を活用することでコスト削減や生産性向上が期待できます。
6.新技術やノウハウの導入
大手企業や先進的な企業に買収されることで、最新の醸造技術やマーケティング手法が導入されます。
これにより、品質向上や生産効率の向上が期待でき、日本酒の競争力が強化されます。
7.伝統技術の継承と保護
日本酒の醸造には、長年培われた伝統技術が欠かせません。
M&Aを通じて、伝統技術を持つ職人の技術や知識が次の世代に継承されやすくなり、これにより地域の文化や歴史も守られることになります。
買い手側のメリット
1.市場シェアの拡大
買収を通じて、日本酒市場におけるシェアを拡大することができます。
特に、地域で強いブランドや老舗の日本酒メーカーを買収することで、新しい商品ラインナップやサービスを追加することができ、事業の多角化も可能になります。
そのブランド力と市場の信頼を即座に取り込むことが可能です。
2.伝統技術とノウハウの取得
日本酒の醸造には独自の技術やノウハウが必要です。
M&Aを通じて、伝統的な醸造技術や高度な技術を持つ職人の技術を取得できるため、製品の品質向上や新商品の開発に役立ちます。
また、買収企業が異業種の場合は、現在新規取得が困難(輸出前提は除く)な清酒製造業の許認可を取得することができます。
3.生産設備と資源の最適化
M&Aにより、買収先の生産設備や供給チェーンを統合し、効率化することができます。
これにより、生産コストの削減や生産効率の向上が期待でき、競争力が強化されます。
4.海外展開の強化
海外市場での需要が高まっている日本酒に対して、M&Aは国際展開を加速する手段となります。
既に海外での販路や知名度を持つ企業を買収することで、海外展開のリスクを低減し、成功の可能性を高めます。
5.人材の確保
日本酒業界には専門的な知識や技術を持つ人材が必要です。
M&Aを通じて、優秀な人材を確保することで、組織全体の能力を高めることができます。
6.シナジー効果の創出
買収先との協力により、研究開発、マーケティング、生産、物流などの各分野でシナジー効果を創出できます。
これにより、全体の効率化と競争力強化が図られます。
酒蔵業界でM&Aを行う際のポイント
酒蔵業界でM&A(合併・買収)を行う際には、特有の要素や業界の特性を考慮する必要があります。
以下に主なポイントをまとめます。
1.規制遵守と許認可の確認
酒類製造、販売に関する法令を遵守し、現状必要な許認可が有効であること、またM&A後においても有効性が継続されることの確認が必要です。
特に、酒造免許や販売免許の名義変更手続きが重要です。
2.醸造技術の継承
日本酒の品質は醸造技術に大きく依存します。
特に、杜氏(とうじ)と呼ばれる専門職の技術や知識は企業の競争力の源です。
M&A後もこれらの技術が失われないよう、従業員や職人との良好な関係を維持し、技術継承を確実に行うことが重要です。
3.季節労働と雇用管理
日本酒の醸造は季節労働が多く、特に冬場に集中することが多いです。
このため、季節ごとの労働力の確保と雇用管理が重要です。
従業員の働きやすい環境を整え、適切な労働条件を提供することで、優秀な人材を確保しやすくなります。
4.生産能力と維持コスト
主要な設備の導入年やメンテナンス履歴、稼働率や生産停止の頻度、故障履歴を確認し、今後必要とされる修繕や設備更新の計画とそのコストを把握します。
また、現在の年間生産量や最大生産能力と、今後を踏まえて複数の製品ラインに対応できるか、季節や需要変動に柔軟に対応できるかなども確認も必要です。
まとめ
酒蔵業界のM&Aをお考えの際は、売却・買収いずれの立場であってもM&Aの専門家へ相談しましょう。
専門家は、豊富な知識、経験をもとに、相談者にマッチする相手先の選定や探索、M&Aの手法の検討を行います。
会社の強み、財務状況、相手先の希望などを整理したうえで相談するとスムーズです。
リガーレは、酒蔵業界のM&Aにも精通しているほか、財務・税務デューデリジェンス、セカンドオピニオンのみの対応も可能ですので、是非お気軽にご相談ください。
この記事の執筆
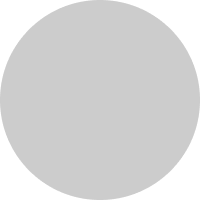
シニアアドバイザー田澤脩平
メガバンクでの法人融資業務を経て、大手M&Aブティックでのアドバイザリー業務ならびに事業会社での買収経験を有する。
