警備業界のM&A動向と最新事例

警備業界は慢性的な人材不足等を背景とした課題可決型のM&A、異業種からの新規参入型M&Aなど、M&Aが活発に行われている業界です。
本記事では、警備業界における市場動向、M&A事例、ならびにM&A成功に向けたポイントについて解説します。
警備業界とは
ここでは、警備業界の概要、業界を取り巻く環境(市場動向/課題)について解説します。
警備業界の概要
警備業は、警備業法に基づき「1号業務(施設警備)」、「2号業務(雑踏・交通誘導警備)」「3号業務(業務設備)」、「4号業務(身辺警護)」」の4種類に大別されます。
多くの警備会社は「1号業務(施設業務)」や「2号業務(雑踏・交通誘導警備)を主に行っており、「3号業務(運搬警備)」や「4号業務(身辺警護)」を行っている事業者は、警備業者の総数に対してそれぞれ7%程度の構成比となっております。それぞれの業務内容は下記ご参照ください。
| 種類 | 内容 |
| 1号業務(施設警備) | 施設(オフィスビル、大型商業施設、工場、学校、公共施設、医療機関など)における、犯罪や事故を防ぐ |
| 2号業務(雑踏・交通誘導警備) | 工事現場や雑踏で交通誘導を行い、事故を防ぐ |
| 3号業務(運搬警備) | 現金・宝石や核燃料物質などの輸送中の紛失や盗難を防ぐ |
| 4号業務(身辺警護) | 警備対象人物の警護を行う |
1号業務の警備方法
| 警備方法 | 内容 |
| 施設警備業務 | オフィスビルや大型商業施設、工場、学校、公共施設、医療施設等に警備員が常駐し、出入管理、巡回、開閉館管理などの業務を行う |
| 巡回警備業務 | 警備員は常駐せず、複数の契約先施設を警備員が車両などで移動し、定期・不定期に巡回する業務 |
| 保安警備業務 | 百貨店、電機量販店、スーパーマーケットなどの商業施設で、私服又は制服警備員による店内巡回、モニターによる監視などを通じて、万引きや置き引きなどの店内犯罪を防止する業務を行う。 |
| 空港保安警備業務 | X線透視検査装置や金属探知機などを用いて、空港機内への持ち込み禁止品の不法な持ち込みを防止する業務を行う。 |
| 機械警備業務 | カメラやビデオ、センサーなどを設置し、監視センターで契約先施設における侵入者や火災などを監視、異常があった場合に警備員が急行し対応する業務を行う。 |
警備業界の市需動向
警備会社の売上高はセキュリティ意識の高まりとともに、2007年まで増加傾向で推移、金融危機の影響で企業における設備投資抑制やコスト管理の厳格化を受け、2009年前後は落ち込んだ。
その後は緩やかな回復に転じたものの、コロナ禍によるテーマパークやイベントの中止・規模縮小に伴い2020年~2021年は2年連続の減少、2022年はコロナ禍からの経済回復がみられ、警備業界の売上高も3年ぶりの増加へ転じた。(売上高約3.5兆円)
また、1号業務における機械警備においては、情報化やセキュリティ機器の高度化により法人・一般家庭ともに需要が増加、市場規模は拡大傾向にある(2020年:推定6,595億円)。

※出所:警察庁生活安全局「警備業の概況」

出所:(公社)日本防犯設備協会「防犯設備推定市場の推移」
警備業界の抱える課題
警備業界特有の課題として、以下2点解説します。
人材不足
特に施設警備や巡回警備等を行う「1号警備」及び、交通誘導や雑踏警備を行う2号警備においては、事業者数も多く、慢性的な人手不足が深刻となっている。(保安に該当する警備業の有効求人倍率5.9倍:2023年5月時点)
人材不足を解消するためには、労働時間や給与水準等の労働条件改善が必要不可欠である。
過当競争
業界トップであるセコム及び第2位のALSOKの合計でシェアは27%程度と大手による寡占度が低い。警備事業者数は1万社超と推計されており、中小規模の警備会社が残70%を奪い合う構図となっており、警備料金の引き下げ等競争が激化している。
今後AIやDX化の推進など、他社との差別化を図る取組みが従来以上に必要となる。
警備業界におけるM&A活用のメリット
警備業界において、M&Aを活用した場合の主なメリットは以下の通りです。
売り手側のメリット
1.後継者問題の解決
2.従業員の雇用継続
3.個人保証・担保の解消
4.売却益(創業者利益)の獲得
5.経営の安定・拡大
6.人材確保がしやすくなる
7.人材教育体制・ノウハウを獲得できる
買い手側のメリット
1.人材を確保できる
2.エリア拡大・販路拡大等の事業シナジーが期待できる
3.ノウハウ・事業・経営資源等時間を掛けずに入手することが可能
警備業界の売却相場
ここでは、警備業界の売却相場について解説します。
コスト・アプローチから見た相場
中小企業におけるM&Aにおいては、時価純資産+営業権(EBITDA×2~4年程度)により算定される価格が一般的な取引レンジとなっております。
(例)時価純資産200百万円 / EBITDA直近3期平均50百万円
200百万円+(50百万円×中央値3年)=350百万円
※EBITDA:営業利益+減価償却費
マーケット・アプローチから見た相場
類似企業比較法により、類似上場企業の財務数値を比較して算定することにより、売却価格相場を把握することも可能となります。
主にEV(事業価値)÷EBITDA倍率を採用することが一般的です。直近における警備業界のEV/EBITDA倍率中央値は3.6倍となっています。
(例)EBITDA50百万円 / 非事業用資産150百万円 / 無借金
EBITDA50百万円×3.6倍+150百万円=330百万円
※売却価格の相場・計算方法は「会社の売却価格・相場を知ろう!会社売却を進める前に必須の知識を徹底解説!」にて詳細に解説しておりますので、ご参照ください。
警備業界のM&A事例
ここでは、警備業界における最近のM&A事例をご紹介します。
M&A事例①(警備業×警備業)
1.共栄セキュリティーサービス(7058)による東邦警備保障の子会社化
施設警備、交通誘導警備等を手掛ける共栄セキュリティーサービス㈱は、同社の連結会社の㈱セキュリティ(埼玉県)を通して、東邦警備保障㈱(埼玉県:売上高146百万円)の全株式を取得し、2024年3月31日付で子会社化した。
東邦警備保障は、同社と同じく施設警備・交通誘導警備及び機械警備事業を展開、将来にわたって強い需要見込みが期待できる関東圏の体制強化を目的に、M&Aを実施。
2.セントラル警備保障(9740)による東亜警備保障の子会社化
施設警備、機械警備等を手掛けるセントラル警備保障㈱は、東亜警備保障㈱の全株式を取得し、2023年4月26日付で子会社化した。
東亜警備保障は、栃木県内を中心に常駐警備、機械警備、運輸警備等を展開している。機械警備事業の強化及び新たなエリアの取り込みを目的に、M&Aを実施。
M&A事例②(異業種×警備業)
1.四国旅客鉄道による東京セフティの子会社化
四国旅客鉄道㈱(以下、「JR四国)という。」は、施設警備・交通誘導警備・イベント警備を手掛ける東京セフティ㈱(香川県)の全株式を取得し、2023年3月29日付で子会社化した。
JR四国は非鉄道事業分野において、ホテル業、駅ビル・不動産事業、飲食・物販事業などを展開。
今回の株式取得により、警備保障業務への参入及びノウハウの獲得を実現するとともに、四国の経済・文化の発展に寄与する地域コングロマリットの形成を目指して、M&Aを実施。
2.センコーグループホールディングス(9069)による日制警備保障の子会社化
センコーグループホールディングス㈱は、大手ゼネコンの建築現場での交通誘導・重機誘導や、常駐警備等を手掛ける日制警備保障㈱(東京都)の全株式を取得し、2023年2月1日付で子会社化した。
センコーグループ物流拠点の警備ニーズに対応するとともに、ハウスメーカー建設現場等のグループ顧客関連警備ニーズに対応することを目的に、M&Aを実施。
警備業界でM&Aを行う際のポイント
最後に、警備業界でM&Aを行う際のポイントを売り手側と買い手側に分けて解説します。
売り手側
1.企業成長の実現
譲渡後に一層の企業成長の実現が期待できるか否かは重要なポイントとなります。
期待できる企業であれば、双方シナジーが高いことが想定されるため、高値での売却に繋がります。
また、企業成長の実現が図れることは従業員の処遇改善や取引先の企業成長にもつながることが期待できます。
2.専門家のサポート
M&Aにおいては多岐に渡る専門知識が必要となります。
M&Aを成功させるためには、信頼できる専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
買い手側
1.売手が抱える課題を把握する
警備業界は、労働集約型産業であることから、未払い残業代の有無、その他簿外債務リスクの検証は必要不可欠であると考えられるため、取引前にデューデリジェンスを実施することをおすすめします。
2.法令順守
警備業界は警備業法に規制される業界であるため、法令順守体制が構築されているかどうかの確認は必要不可欠となります。
3.シナジー効果について調査
買収により、買手企業、買収対象会社双方にどのようなシナジー効果が期待できるかを精査することが重要です。
既存取引先に新たなサービスが展開できる、スケールメリットにより業務の効率化やコスト削減が実現できる等、具体的かつ定量的に分析・検証することが重要となります。
まとめ
警備会社の売却・買収などをお考えの際は、まずM&A専門家へ相談しましょう。
専門家は、豊富な知識、経験をもとに、相談者にマッチする相手先の探索や、M&A手法の検討を行います。
リガーレは、警備業界のM&Aにも精通しているほか、財務・税務デューデリジェンスにもご対応可能ですので、是非お気軽にご相談ください。
この記事の執筆
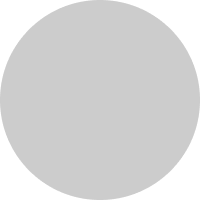
シニアアドバイザー清水洋伸
メガバンクでのファイナンス業務を経て、アドバイザリー業務並びに財務デューデリジェンス業務に従事。
